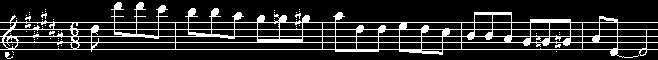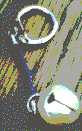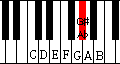>> まずはじめに <<

それは今のわたしを作り上げた元凶
そしてピアノを弾く誰もが憧れる旋律
もしこの曲に出逢っていなければ私は一生
クラシックの魅力に目覚めはしなかったろう…
この“鐘の音”は初めて聴いた数年前から
ずっと私の中で鳴り響いて止むことは一秒もなかった…
他学科であるにもかかわらず
大学のピアノ練習室にひきこもり授業をサボっては
一日8時間は当然にして毎日狂ったように
夜10時までピアノを弾いていた…
それはまるでピアノに目覚めるのが遅すぎた時間を
やっきになって取り戻そうとでもするかのようだった…
私はまだ演奏中にピアノの弦を切ったことはないけれど
初めてその弦が切れる日はこのラ・カンパネラを弾いている時で
おそらく後半の小節に存在する“激しくオクターブ”の瞬間だろう
【嬰ニ】の2本が“逝く”と思われる…
そして現在…なおもわたくしはこの曲に執着している
4年の月日を経てやっとカタチになってきた“我がラ・カンパネラ”には
いつか誰かの心に響いてくれる日は来るのだろうか…
願わくば… どうかわたしの鳴らすこの“鐘”が
これから夢に挑もうとするアマチュア達の大きな力となりますように…

▲ 上へ