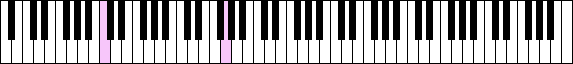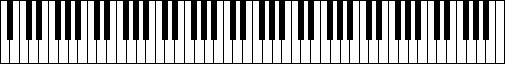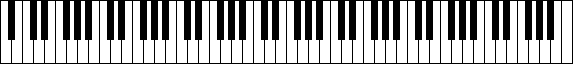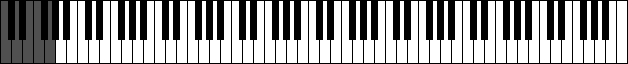>>
HOME
>>
研究室TOP
>>
戻る
■ピアノの鍵盤について
ピアノは非常に音域が広く、オーケストラの音域のほぼ全てをこなせるため、
クラシック音楽の多くはピアノ曲に編曲して演奏することができます。
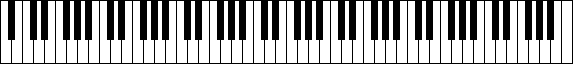
標準のピアノで、 下2点イ(ラ)[※MIDI] から
下2点イ(ラ)[※MIDI] から
 5点ハ(ド)[※MIDI]までの7と1/4オクターヴの88鍵盤で構成されています。
黒鍵は36個、白鍵は52個です。黒鍵の幅は9.5mm、白鍵の幅は22.5mmあります。
現代のピアノはどれもすべて“12等分平均律”に調律されているため、♯(シャープ)だろうが♭(フラット)だろうが黒鍵や白鍵に関わらず
5点ハ(ド)[※MIDI]までの7と1/4オクターヴの88鍵盤で構成されています。
黒鍵は36個、白鍵は52個です。黒鍵の幅は9.5mm、白鍵の幅は22.5mmあります。
現代のピアノはどれもすべて“12等分平均律”に調律されているため、♯(シャープ)だろうが♭(フラット)だろうが黒鍵や白鍵に関わらず
 隣あう鍵盤の“音程の幅”は完全に一致し、すべて“半音”の関係[※MIDI]にあります。
隣あう鍵盤の“音程の幅”は完全に一致し、すべて“半音”の関係[※MIDI]にあります。
ピアノを始めたばかりの人はどこがドの音なのか分からないと思いますが、鍵盤は、
“黒鍵が5個、白鍵が7個の計12個のカタマリ”の繰り返し(=周期)で作られていることに気付けば、あとは簡単です。
ドとファの“鍵盤の形”は似ていますが、黒鍵が2個の方をド、黒鍵が3個の方をファと覚えるとよいでしょう。
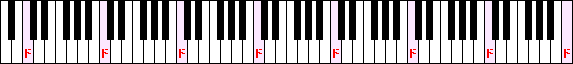
ところで、
黒鍵の幅は白鍵の幅に比べて少し細めにできているため、音を外しやすく、
そのせいでピアノの初心者など…とくに子供には嫌われているみたいです(笑) 例⇒「ヽ(`Д´)ノ ウワァァァァン! 黒鍵や〜だ〜」
だけどピアノは、その“嫌われ者の黒鍵”がなければどこが何の音なのかわからなくなってしまうんです。
88個の鍵盤がすべて白鍵だけで構成された凹凸のない真っ平らなピアノを想像してみてください。
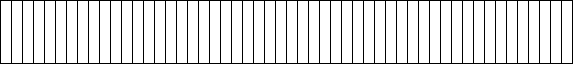
└→ “ミ”どこ?“シ”どこ? o(゚д゚o≡o゚д゚)o っていうか“ド”はどこよ?
そう…みなさんは、5つの黒鍵があるおかげで
どこに何の音があるのかを瞬時に知ることができ、ピアノを演奏できるわけです。
…あ( ̄□ ̄;)!!
―ハイ、これでは鍵盤が52個しかありません。
では、正確に88個ならべてみましょう。フレーム内におさまらないので□こちらをどうぞ。
この場合、ドから次のドまで(1オクターヴ)がどれぐらいの幅になるのか計算してみました。白鍵ひとつあたりの幅を22.5mm(ヤマハピアノ)だと仮定し、“鍵盤の間の隙間”は1mmも無いものとします。
22.5(mm) × 13(個) = 292.5(mm) ⇒約29cm( ̄□ ̄;)!!
それは普通のピアノで、ドから次のドを越えたところのソ♯(=ラ♭)までの幅にあたり、
まず通常の人間ではオクターヴを叩くことができません。さらに“最低音から最高音までの幅”を単純に計算してください。22.5×88=?
両腕をまっすぐ広げて2mある人いますか? ラピュタのロボットじゃあるまいし…。。。
ラピュタのロボットじゃあるまいし…。。。
黒鍵が黒くて細いのは、“凸凹のカタチ”をしているのには、そんな理由があったんです。
さて、
むっかーしむかしのピアノについて…
 チェンバロや作られたばかりの初期のピアノには、鍵盤がたったの4オクターヴぐらいしかありませんでした。
現代で例えるなら、「おもちゃ」ですね。しかも黒鍵と白鍵の色が逆でした。(⇒)
チェンバロや作られたばかりの初期のピアノには、鍵盤がたったの4オクターヴぐらいしかありませんでした。
現代で例えるなら、「おもちゃ」ですね。しかも黒鍵と白鍵の色が逆でした。(⇒)
これには2つの説があり、
【白盤に使う「象牙(ぞうげ)」が高価で貴重だったため安い「黒檀(こくたん)」の黒盤の方を多くした】という説と
【女性の白い手が美しく映える黒い鍵盤を多くした】という説があるようです。
でもピアノは今や白と黒が逆。
白鍵は安いプラスチックで代用できるし黒鍵が多いよりは白鍵が多い方が演奏者にとっては鍵盤が見やすいですからね。
鍵盤の数も時代とともにピアノが進化し増えていき、現在の88鍵盤に落ち着きました。
ちなみにベートーヴェンはピアノを寄贈されると、そのピアノの性能(=音域)を最大に活用して作曲したそうです。
彼のピアノソナタ【 月光 】を弾いてごらんなさい。ほら、5オクターヴにおさまったでしょ?
彼がその曲を作った時に所持していたピアノが5オクターブのシュタインだったからです。
【 ワルトシュタイン 】は5オクターブ+4度をすべて使った曲ですが、エラール社からもらったピアノで作ったからです。
さらに6オクターブのブロードウッド社のピアノで、彼は【 熱情 】を作りました。
もともとピアノの“鍵盤の幅”は身体の大きな“外人の手”を標準に作られており、
そのピアノを小さな身体(手)の日本人が彼らと同じように弾きこなすのが難しいのは当前です。
ヴァイオリンには子供用の小さいものがあり、身体の成長とともにとり換えていきますが、ピアノはそうはいきません。
このようなハンデを乗り越えてチャイコンで優勝した日本人・上原彩子はまさにすごいことだといえるでしょう。
逆に巨大な手といえばラフマニノフですが、彼は12度の音階を左手で押さえることができたそうです。
つまり左の小指でドの音を押しながら、親指で1オクターブ半上のソの音を鳴らすわけです(↓)…ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル…恐ろしい
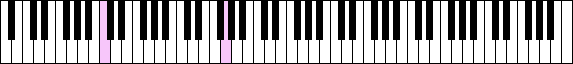
└→ “ド”と1オクターヴ半上の“ソ”(※MIDI)
“ド”と1オクターヴ半上の“ソ”(※MIDI)
ちなみにカワイのアップライトは、他社に比べ黒鍵も白鍵も、全体的に鍵盤の幅が狭いです。
これはひょっとして、かわいそうな日本人の手に合わせて作られているのでしょうか(´・ω・`)?
└→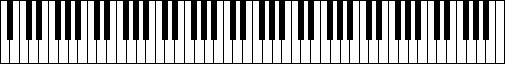
さて、
こっからは「鍵盤って、もっと多くてもいいんでないの?」という人のために…。
「ピアノ」がなぜ88個の鍵盤で安定したのか理由をいくつかご説明いたしましょう。
―88個の鍵盤のうち、 一番上の音(ド)[※MIDI]を叩いてみてください―
一番上の音(ド)[※MIDI]を叩いてみてください―
『ピン♪』という、石を叩いたような音がしませんか?
そして、音程がよく分からなくはないですか?
―今度は、 一番下(ラ)の音[※MIDI]を叩いてみてください―
一番下(ラ)の音[※MIDI]を叩いてみてください―
『ボコーン♪』という、なんだか濁った音がしませんか?
そして、音程がよく分からなくはないですか?
そう…通常の人間の耳には現時点(88鍵盤)ですでに、最高音と最低音の他の音との音程の区別がつかないのです。
音としては聴こえますが、音程をギリギリ認識できる限界が、この2つのラ(最低音)とド(最高音)なのです。
つまりそれ以上に鍵盤を増やしても、もはや意味がないということです。
ところが…
ベーゼンドルファーのフルコンサートグランドピアノ【MODELL290】には、なんと鍵盤が97個あります。
今までの88鍵盤の 低音側に「黒鍵&白鍵」を含めた9個の鍵盤(エクステンドベース)[※MIDI]を延長して
低音側に「黒鍵&白鍵」を含めた9個の鍵盤(エクステンドベース)[※MIDI]を延長して
 完全8オクターヴ[※MIDI]になっているのです。ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル…美しい…
完全8オクターヴ[※MIDI]になっているのです。ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル…美しい…
「エクステンド」は、「拡張する」「増やす」という意味があるので、「エクステンドベース」の直訳は“拡張した低音”でしょうか。
これは昔、ブゾーニがバッハの曲を編曲していたときに、どうしても通常のピアノでは表現できない音があったため、
ベーゼンドルファーに相談したのがきっかけだといいます。
“その鍵盤(=エクステンドベース)”は弾くのが目的ではなく、 “共鳴による倍音の発生”[※MIDI]を狙って作られたものです。
簡単に言っちゃうと、要は、たとえ弾かなくてもピアノの内部に9本の太い弦が増えたおかげで、
他の鍵盤(特に中低音)の音にさらなる“豊かな響き”が生まれるというしくみです。
だけど一部のピアニストには「中低音の響きが豊かになりすぎてその音域が目立ってしまい、高音部の響きが物足りなく感じられる」とも言われており、
そのため、この「インペリアル」はプロでさえ弾きこなすのが難しいと言われています。通常のピアノとは“音の性格”がまったく異なるピアノです。(ニュータイプ専用?
“共鳴による倍音の発生”[※MIDI]を狙って作られたものです。
簡単に言っちゃうと、要は、たとえ弾かなくてもピアノの内部に9本の太い弦が増えたおかげで、
他の鍵盤(特に中低音)の音にさらなる“豊かな響き”が生まれるというしくみです。
だけど一部のピアニストには「中低音の響きが豊かになりすぎてその音域が目立ってしまい、高音部の響きが物足りなく感じられる」とも言われており、
そのため、この「インペリアル」はプロでさえ弾きこなすのが難しいと言われています。通常のピアノとは“音の性格”がまったく異なるピアノです。(ニュータイプ専用?
ちなみに、実物を見たことはありませんが、エクステンドベース(増えた9個の鍵盤)の白鍵は間違って弾かないように黒く塗ってあるそうです。
左側に鍵盤が増えることによる空間的な感覚の混乱を防ぐ意味もあります。
昔は、黒く塗るかわりに専用の蓋が付いていたという話です。
当時、いつもピアノを壊してしまうフランツ・リストの激しい演奏に耐えた唯一のピアノがベーゼンドルファーだったという話は有名ですが、
その中でも【インペリアル(Imperial)】は、ベーゼンドルファー社、最上級のグランドピアノです。
その意味は「皇帝」。オーストリアが国交のときに、相手国の国王などに装飾をほどこしたベーゼンドルファー社のグランドピアノを献上したことからこの名がついたとか。
ちなみに日本の“皇室”にもオーストリアから献上されたインペリアルが置いてあるそうです。
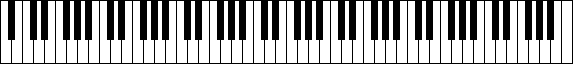
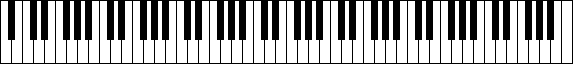
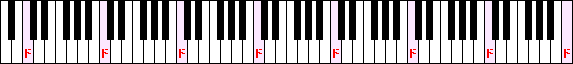
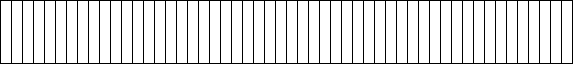
 チェンバロや作られたばかりの初期のピアノには、鍵盤がたったの4オクターヴぐらいしかありませんでした。
現代で例えるなら、「おもちゃ」ですね。しかも黒鍵と白鍵の色が逆でした。(⇒)
チェンバロや作られたばかりの初期のピアノには、鍵盤がたったの4オクターヴぐらいしかありませんでした。
現代で例えるなら、「おもちゃ」ですね。しかも黒鍵と白鍵の色が逆でした。(⇒)